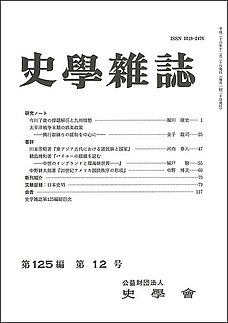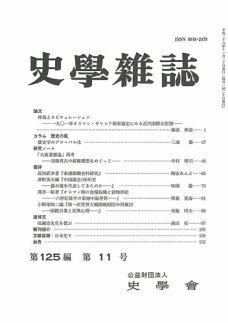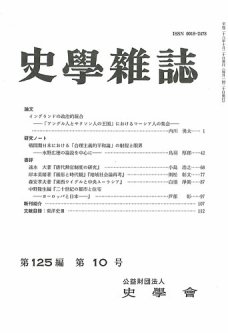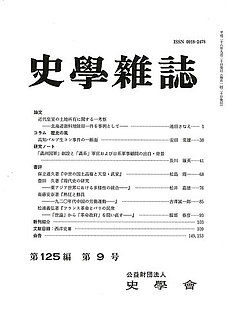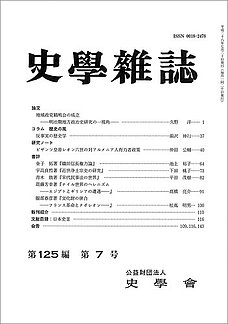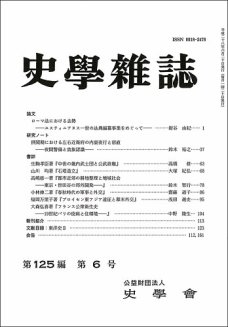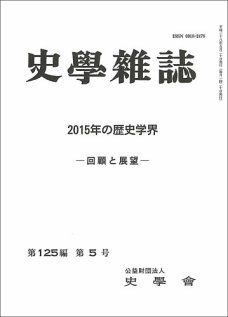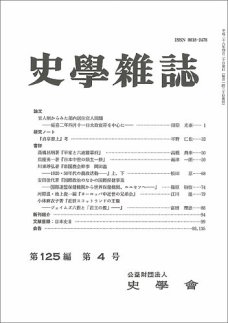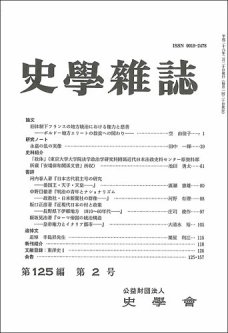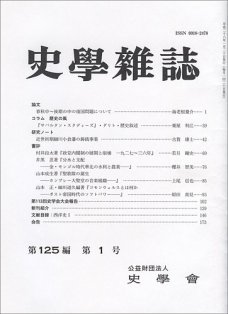125編第12号
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 川本芳昭著『東アジア古代における諸民族と国家』(汲古叢書 124) | 河内 春人 | 47(2011) | |
| 鶴島博和著『バイユーの綴織を読む――中世のイングランドと環海峡世界――』 | 城戸 毅 | 55(2019) | |
| 中野耕太郎著『20世紀アメリカ国民秩序の形成』 | 中野 博文 | 60(2024) | |
|
新刊紹介 | |||
| 福嶋紀子著『赤米のたどった道――もうひとつの日本のコメ――』 | 渡邊 浩貴 | 70(2034) | |
| 瀬田勝哉編『変貌する北野天満宮――中世後期の神仏の世界――』 | 坂井 武尊 | 71(2035) | |
| 渡邉義浩編『中国史の時代区分の現在』(第六回日中学者中国古代史論壇論文集) | 板橋 暁子 | 73(2037) | |
| 氣賀澤保規編『隋唐佛教社會の基層構造の研究』(明治大学東洋史資料叢刊 12) | 朴 周恩 | 74(2038) | |
| 髙畠純夫著『ペロポネソス戦争』 | 齋藤 貴弘 | 75(2039) | |
| レギーナ・ミュールホイザー著/姫岡とし子監訳『戦場の性――独ソ戦下のドイツ兵と女性たち』 | 見目 典隆 | 76(2040) | |
| 長谷川貴彦著『現代歴史学への展望――言語論的転回を超えて――』 | 長谷川祐平 | 77(2041) | |
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅵ |
79(2043) |
||
|
会告 | |||
|
|
117(2081) |
||
|
史学雑誌第125編総目次 | |||
125編第11号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
"仲裁とカピチュレーション ――一九〇一年オスマン・ギリシア領事協定にみる近代国際思想――" |
|
藤波 伸嘉 |
1(1813) |
|
|
コラム 歴史の風 | ||||
| 歴史学のグローバル化 | 三浦 徹 | 37(1849) | ||
|
研究ノート | ||||
| 「大坂遷都論」再考――羽柴秀吉の政権構想をめぐって―― | |
中村 博司 | 40(1852) | |
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 高村武幸著『秦漢簡牘史料研究』(汲古叢書 128) | 陶安あんど | 65(1877) | |
| 深町英夫編『中国議会100年史――誰が誰を代表してきたのか――』 | 味岡 徹 | 73(1885) | |
| 澤井一彰著『オスマン朝の食糧危機と穀物供給――一六世紀後半の東地中海世界――』(山川歴史モノグラフ 30) | 齊藤 寛海 | 81(1893) | |
| 小野塚知二編『第一次世界大戦開戦原因の再検討――国際分業と民衆倫理――』 | 布施 将夫 | 89(1901) | |
|
追悼文 | |||
| 成瀬治先生を偲ぶ | 森田 安一 | 97(1909) | |
|
新刊紹介 | |||
| 滝川幸司著『菅原道真論』 | 有富 純也 | 100(1912) | |
| 奈良国立博物館・東京文化財研究所編『大徳寺伝来五百羅漢図』 | 藤原 重雄 | 101(1913) | |
| 黒板伸夫・永井路子編『黒板勝美の思い出と私たちの歴史探究』 | 中野 弘喜 | 103(1915) | |
| 中谷直司著『強いアメリカと弱いアメリカの狭間で――第一次世界大戦後の東アジア秩序をめぐる日米英関係――』 | 吉田ますみ | 104(1916) | |
| 川越泰博編『様々なる変乱の中国史』 | 宮内 勇弥 | 105(1917) | |
| 樺山紘一著『ヨーロッパ近代文明の曙――描かれたオランダ黄金世紀――』 | 深谷 訓子 | 106(1918) | |
| 志村真幸編『異端者たちのイギリス』 | 小野寺瑶子 | 107(1919) | |
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅴ |
107(1919) |
||
125編第10号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
イングランドの政治的統合――「アングル人とサクソン人の王国」におけるマーシア人の集会―― |
|
内川 勇太 |
1(1675) |
|
|
研究ノート | ||||
| 戦間期日本における「合理主義的平和論」の射程と限界 ――水野広徳の論説を中心に―― |
|
鳥羽 厚郎 | 42(1716) | |
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 速水 大著『唐代勲官制度の研究』(汲古叢書 122) | 小島 浩之 | 68(1742) | |
| 岸本美緒著『風俗と時代観』『地域社会論再考』〈明清史論集 1、2〉(研文選書 112、113) | 則松 彰文 | 77(1751) | |
| 森安孝夫著『東西ウイグルと中央ユーラシア』 | 白須 淨眞 | 87(1761) | |
| 中野隆生編『二十世紀の都市と住宅――ヨーロッパと日本――』 | 芦部 彰 | 97(1771) | |
|
新刊紹介 | |||
| 稲田奈津子著『日本古代の喪葬儀礼と律令制』 | 山下 洋平 | 107(1781) | |
| 朴 敬玉著『近代中国東北地域の朝鮮人移民と農業』 | 白田 拓郎 | 108(1782) | |
| ボヤント著『内モンゴルから見た中国現代史――ホルチン左翼後旗の「民族自治」――』 | 広川 佐保 | 109(1783) | |
| 井上秀太郎 | 110(1784) | ||
|
文献目録 | |||
|
東洋史Ⅲ |
112(1786) |
||
125編第9号
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
「満洲国軍」創設と「満系」軍官および日系軍事顧問の出自・背景 |
|
及川 琢英 |
41(1561) |
|
書評 | |||
|
保立道久著『中世の国土高権と天皇・武家』(歴史科学叢書) |
松島 周一 |
68(1588) |
|
|
豊田 久著『周代史の研究――東アジア世界における多様性の統合』(汲古叢書 123) |
松井 嘉徳 |
76(1596) |
|
|
衛藤安奈著『熱狂と動員――一九二〇年代中国の労働運動――』 |
吉澤誠一郎 |
85(1605) |
|
|
松浦義弘著『フランス革命とパリの民衆――「世論」から「革命政府」を問い直す――』 |
服部 春彦 |
93(1613) |
|
|
新刊紹介 | |||
|
田中禎昭著『日本古代の年齢集団と地域社会』 |
浅野 啓介 |
103(1623) |
|
|
神田裕理著『戦国・織豊期朝廷の政務運営と公武関係』(日本史史料研究会研究選書 9) |
中山 翠 |
104(1624) |
|
|
外務省編纂『日本外交文書 昭和期III』第三巻 昭和十二~十六年 移民問題・雑件 |
吉井 文美 |
105(1625) |
|
|
大澤正昭・中林広一編『春耕のとき――中国農業史研究からの出発――』 |
田熊 敬之 |
106(1626) |
|
|
横手慎二著『スターリン――「非道の独裁者」の実像――』 (中公新書) |
石井 規衛 |
107(1627) |
|
|
文献目録 | |||
|
西洋史Ⅲ |
109(1629) |
||
|
会告 | |||
|
149(1669),153(1673)
|
|||
125編第8号
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
第一次世界大戦と税財政政策 |
|
諸橋 英一 |
37(1395) |
|
台湾における寄生虫対策と日本の医療協力(一九六〇年代から一九七〇年代) |
|
井上 弘樹 |
61(1419) |
|
書評 | |||
|
若江賢三著『秦漢律と文帝の刑法改革の研究』(汲古叢書 118) |
水間 大輔 |
88(1446) |
|
|
南 修平著『アメリカを創る男たち――ニューヨーク建設労働者の生活世界と「愛国主義」――』 |
立林奈々子 |
98(1456) |
|
|
新刊紹介 | |||
|
北村安裕著『日本古代の大土地経営と社会』(同成社古代史選書 17) |
垣中 健志 |
107(1465) |
|
|
大阪市立大学豊臣期大坂研究会編、大澤研一・仁木宏・松尾信裕監修『秀吉と大坂――城と城下町――』(上方文庫別巻シリーズ 6) |
高橋慎一朗 |
108(1466) |
|
|
石井知章編『現代中国のリベラリズム思潮――一九二〇年代から二〇一五年まで――』 |
衛藤 安奈 |
109(1467) |
|
|
『イタリア建築紀行――ゲーテと旅する七つの都市――』 |
赤松加寿江 |
110(1468) |
|
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅳ |
112(1470) |
||
|
会告 | |||
|
161(1519)
|
|||
125編第7号
|
コラム 歴史の風 | |||
|---|---|---|---|
|
反事実の歴史学 |
前沢 伸行 |
37(1251) |
|
|
研究ノート | |||
|
ビザンツ皇帝レオン六世の対アルメニア人有力者政策 |
|
仲田 公輔 |
40(1254) |
|
書評 | |||
|
金子 拓著『織田信長権力論』 |
池上 裕子 |
64(1278) |
|
|
宇高良哲著『近世浄土宗史の研究』 |
下田 桃子 |
73(1287) |
|
|
青木 敦著『宋代民事法の世界』 |
平田 茂樹 |
82(1296) |
|
|
周藤芳幸著『ナイル世界のヘレニズム――エジプトとギリシアの遭遇――』 |
髙橋 亮介 |
91(1305) |
|
| 服部春彦著『文化財の併合――フランス革命とナポレオン』 |
松嶌 明男 |
100(1314) |
|
|
新刊紹介 | |||
|
沖森卓也・佐藤信・矢嶋泉編『新校古事記』 |
中野 謙一 |
110(1324) |
|
|
水野章二著『里山の成立――中世の環境と資源――』 |
貴田 潔 |
111(1325) |
|
|
伊藤敏雄・窪添慶文・關尾史郎編『湖南出土簡牘とその社会』 |
新津健一郎 |
112(1326) |
|
|
土田哲夫編著『近現代東アジアの文化と政治』(中央大学政策文化総合研究所研究叢書 19) |
福士 由紀 |
113(1327) |
|
|
小澤卓也・田中聡・水野博子編著『教養のための現代史入門』 |
百瀬 亮司 |
114(1328) |
|
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅲ |
116(1330) |
||
|
会告 | |||
|
109(1323),116(1330),143(1357)
|
|||
125編第6号
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
|
生駒孝臣著『中世の畿内武士団と公武政権』 |
高橋 修 |
63(1115) |
|
|
山川 均著『石塔造立』 |
大塚 紀弘 |
68(1120) |
|
|
高嶋修一著『都市近郊の耕作整理と地域社会 |
鈴木 智行 |
78(1130) |
|
|
小林伸二著『春秋時代の軍事と外交』(汲古叢書 121) |
齋藤 道子 |
86(1138) |
|
|
福岡万里子著『プロイセン東アジア遠征と幕末外交』 |
浅田 進史 |
95(1147) |
|
|
大森弘喜著『フランス公衆衛生史――19世紀パリの疫病と住環境――』(学術叢書) |
中野 隆生 |
104(1156) |
|
|
新刊紹介 | |||
|
渡部育子著『律令国司制の成立』(同成社古代史選書 14) |
井上 翔 |
113(1165) |
|
|
早島大祐編『西山地蔵院文書』(京都大学史料叢書 6) |
川本 慎自 |
114(1166) |
|
|
横浜外国人社会研究会・横浜開港資料館編 |
古結 諒子 |
116(1168) |
|
|
平勢隆郎・塩沢裕仁編『関野貞大陸調査と現在』Ⅰ・Ⅱ、平勢隆郎・塩沢裕仁・関紀子・野久保雅嗣編『東方文化学院旧蔵建築写真目録』、田良島哲・平勢隆郎・三輪紫都香編『東京国立博物館所蔵竹島卓一旧蔵「中国史跡写真」目録』 |
板橋 暁子 |
117(1169) |
|
|
宋代史研究会編『中国伝統社会への視角』(宋代史研究会研究報告 10) |
付 晨晨 |
118(1170) |
|
|
山中由里子編『〈驚異〉の文化史――中東とヨーロッパを中心に――』 |
徳永 佳晃 |
119(1171) |
|
|
杉本淑彦・竹中幸史編著『教養のフランス近現代史』 |
長野 壮一 |
120(1172) |
|
|
大森一輝著『アフリカ系アメリカ人という困難 ――解放奴隷後の黒人知識人と「人種」――』 |
土屋 和代 |
121(1173) |
|
|
文献目録 | |||
|
東洋史Ⅱ |
123(1175) |
||
|
会告 | |||
| 112(1164),161(1213) | |||
125編第5号 回顧と展望
|
総説 |
| ||
|---|---|---|---|
|
佐藤 信 |
1(629) |
||
|
歴史理論 | |||
|
千葉 敏之 |
6(634) |
||
|
日本史 | |||
|---|---|---|---|
|
考 古 |
及川 穣 西村 広経 篠原 和大 山本 亮 村山 卓 |
11(639) |
|
|
古 代 |
新川登亀男 加藤 謙吉 鈴木 正信 十川 陽一 亀谷 弘明 |
37(665) |
|
|
中 世 |
桜井 英治 佐藤 雄基 堀川 康史 畑山 周平 谷口 雄太 |
72(700) |
|
| 近 世 |
根岸 茂夫 堀越 祐一 矢部健太郎 佐藤 孝之 高田 綾子 |
105(733) |
|
|
近現代 |
土田 宏成 寺島 宏貴 團藤 充己 安原 徹也 原口 大輔 |
152(780) |
|
|
中 国 |
|||
|
殷・周・春秋 |
松本 圭太 |
197(825) |
|
|
戦国・秦漢 |
目黒 杏子 |
203(821) |
|
|
魏晋南北朝 |
三浦 雄城 |
209(837) |
|
|
隋・唐 |
速水 大 |
215(843) |
|
|
五代・宋・元 |
小林 隆道 |
222(850) |
|
|
明・清 |
岡本 弘道 |
229(857) |
|
|
近代 |
森川 裕貫 |
235(863) |
|
|
現代 |
関 智英 |
243(871) |
|
|
台湾 |
家永 真幸 |
250(878) |
|
|
朝 鮮 |
井上 直樹 川西 裕也 原 智弘 |
252(880) |
|
|
内陸アジア | ||
|---|---|---|
|
齊藤 茂雄 青木 雅浩 |
262(890) |
|
|
東南アジア | ||
|
大久保翔平 |
273(901) |
|
|
南アジア | ||
|
嘉藤 慎作 原 孝一郎 |
280(908) |
|
|
西アジア・北アフリカ | ||
|
田澤 恵子 有松 唯 橋爪 烈 佐々木 紳 |
289(917) |
|
|
アフリカ | ||
|
澤田 望 |
307(935) |
|
|
ヨーロッパ | |||
|---|---|---|---|
|
古 代 |
|||
|
ギリシア |
師尾 晶子 |
311(939) |
|
|
ローマ |
浦野 聡 |
315(943) |
|
|
中 世 |
|||
|
一般 |
図師 宣忠 |
319(947) |
|
|
西欧・南欧 |
図師 宣忠 |
320(948) |
|
|
中東欧・北欧 |
松本 涼 |
325(953) |
|
|
イギリス |
古城真由美 |
329(957) |
|
|
ロシア・ビザンツ |
西村 道也 |
333(961) |
|
|
近 代 |
|||
|
一般 |
秋山 晋吾 |
335(963) |
|
|
イギリス |
山本信太郎 中村 武司 |
337(965) |
|
|
フランス |
仲松 優子 |
344(972) |
|
|
ドイツ・スイス・ネーデルラント |
蝶野 立彦 |
351(979) |
|
|
ロシア・東欧・北欧 |
中澤 達哉 |
358(986) |
|
|
南欧 |
北田 葉子 |
362(990) |
|
|
現 代 |
|||
|
一般 |
小関 隆 |
366(994) |
|
|
イギリス |
川本 真浩 |
369(997) |
|
|
フランス |
鳥潟 優子 |
372(1000) |
|
|
ドイツ・スイス・ネーデルラント |
星乃 治彦 今井 宏昌 |
378(1006) |
|
|
ロシア・東欧・北欧 |
麻田 雅文 |
384(1012) |
|
|
アメリカ | |||
|
北アメリカ |
柳生 智子 寺田 由美 |
390(1018) |
|
|
ラテン・アメリカ |
矢澤 達宏 |
398(1026) |
|
|
編集後記 | |||
|
404(1032) |
|||
|
文献目録 | |||
|
西洋史II |
405(1033) |
||
|
会告 | |||
|
196(824),288(916) |
|||
125編第4号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
官人制からみた部内居住官人問題――延喜二年四月十一日太政官符を中心に―― |
|
田原 光泰 |
1(491) |
|
|
研究ノート | ||||
|
『貞享書上』考 |
|
平野 仁也 |
32(522) |
|
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
|
髙橋昌明著『平家と六波羅幕府』 |
高橋 典幸 |
50(540) |
|
|
呉座勇一著『日本中世の領主一揆』 |
海津 一朗 |
59(549) |
|
|
川東竫弘著『帝国農会幹事 岡田温――1920・30年代の農政活動――』上・下(松山大学研究叢書 81・82) |
松田 忍 |
74(564) |
|
|
安田佳代著『国際政治のなかの国際保健事業――国際連盟保健機関から世界保健機関、ユニセフへ――』(MINERVA人文・社会科学叢書 198) |
篠原 初枝 |
68(558) |
|
|
河原 温・池上俊一編『ヨーロッパ中近世の兄弟会』 |
江川 温 |
79(569) |
|
|
新刊紹介 | |||
|
〈史学会125周年リレーシンポジウム〉 |
島田 竜登 |
94(584) |
|
|
東北史学会・福島大学史学会・公益財団法人史学会編『東北史を開く』 |
榎本 渉 |
95(585) |
|
|
公益財団法人史学会編『災害・環境から戦争を読む』 |
千葉 功 |
96(586) |
|
|
九州史学会・公益財団法人史学会編『過去を伝える、今を遺す――歴史資料、文化遺産、情報資源は誰のものか――』 |
中野目 徹 |
97(587) |
|
|
文献目録 | |||
|
日本史I |
99(589) |
||
|
会告 | |||
|
93(583),135(625) |
|||
125編第3号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
近衛新体制期の企画院と予算編成 |
中村 陵
|
1(337)
|
||
|
コラム 歴史の風 | ||||
|
「オホーツク海岸の冬ごもり」から春さり来れば |
熊木 俊朗 |
36(372) |
||
|
研究動向 | |||
|---|---|---|---|
|
感情史を考える |
森田 直子 |
39(375) |
|
|
書評 | |||
|
志村佳名子著『日本古代の王宮構造と政務・儀礼』 |
吉田 歓 |
58(394) |
|
|
木下昌規著『戦国期足利将軍家の権力構造』(中世史研究叢書 27) |
谷口 雄太 |
66(402) |
|
|
武石典史著『近代東京の私立中学校――上京と立身出世の社会史――』(MINERVA人文・社会科学叢書 173) |
稲井 智義 |
75(411) |
|
|
森川裕貫著『政論家の矜持――中華民国時期における章士釗と張東〓の政治思想――』 |
水羽 信男 |
83(419) |
|
|
橋本伸也・沢山美果子編『保護と遺棄の子ども史』(叢書・比較教育社会史) |
天野知恵子 |
89(425) |
|
|
新刊紹介 | |||
|
松方冬子編『日蘭関係史をよみとく』上巻 つなぐ人々、フレデリック・クレインス編『日蘭関係史をよみとく』下巻 運ばれる情報と物 |
鳥井裕美子 |
97(433) |
|
|
菅良樹著『近世京都・大坂の幕府支配機構――所司代 城代 定番 町奉行――』 |
廣瀬 翔太 |
99(435) |
|
|
池田雄一編『漢代を遡る奏〓――中国古代の裁判記録――』 |
石原 遼平 |
100(436) |
|
|
土肥義和編『八世紀末期~十一世紀初期 燉煌氏族人名集成――氏族人名篇 人名篇――』 |
三浦 雄城 |
101(437) |
|
|
木村靖二・千葉敏之・西山暁義編『ドイツ史研究入門』 |
姫岡 とし子 |
102(438) |
|
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅰ |
104(440) |
||
|
会告 | |||
|
103(439),152(488) |
|||
125編第2号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
旧体制下フランスの地方統治における権力と慈善
|
空 由佳子 |
1(177) | ||
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
永嘉の乱の実像 |
|
田中 一輝 |
39(215) |
|
「政体」(東京大学大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター原資料部 所蔵「安場保和関係文書」所収) |
池田 勇太 |
61(237) |
|
|
書評 | |||
|
河内春人著『日本古代君主号の研究――倭国王・天子・天皇――』 |
廣瀬 憲雄 |
80(256) |
|
|
中野目徹著『明治の青年とナショナリズム――政教社・日本新聞社の群像――』 |
河野 有理 |
88(264) |
|
| 坂口正彦著『近現代日本の村と政策――長野県下伊那地方 1910~60年代――』 |
庄司 俊作 |
97(273) |
|
|
飯坂晃治著『ローマ皇帝の統治構造――皇帝権力とイタリア都市――』 |
大清水 裕 |
105(281) |
|
|
追悼文 | |||
|
追悼 辛島昇先生 |
粟屋 利江 |
115(291) |
|
|
新刊紹介 | |||
|
服藤早苗著『平安王朝の五節舞姫・童女――天皇と大嘗祭・新嘗祭――』(塙選書 120) |
内野 恵佑 |
118(294) |
|
|
鰐淵寺文書研究会編『出雲鰐淵寺文書』 |
長谷川博史 |
119(295) |
|
|
彭 浩著『近世日清通商関係史』 |
松方 冬子 |
120(296) |
|
|
戸部健著『近代天津の「社会教育」――教育と宣伝のあいだ――』(静岡大学人文社会科学部研究叢書 48) |
岩間 一弘 |
121(297) |
|
|
東洋文庫編『東インド会社とアジアの海賊』 |
大久保翔平 |
123(299) |
|
|
油井大三郎・藤田進著『21世紀の課題――グローバリゼーションと周辺化――』(21世紀歴史学の創造 7) |
池田 嘉郎 |
124(300) |
|
|
文献目録 | |||
|
東洋史Ⅰ |
126(302) |
||
|
会告 | |||
|
125(301),157(333) |
|||
125編第1号
|
論文 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 春秋中~後期の申の復国問題について |
海老根量介 |
1(1) |
|||
|
|
|||||
|
コラム 歴史の風 | |||
|---|---|---|---|
|
『サバルタン・スタディーズ』・ダリト・歴史叙述 |
粟屋 利江 |
39(39) |
|
|
研究ノート | |||
|
近世初期細川小倉藩の鋳銭事業 |
|
古賀 康士 |
42(42) |
|
書評 | |||
|
村井良太著『政党内閣制の展開と崩壊 一九二七~三六年』 |
若月 剛史 |
69(69) |
|
|
井黒 忍著『分水と支配――金・モンゴル時代華北の水利と農業――』 |
櫻井 智美 |
76(76) |
|
|
山本成生著『聖歌隊の誕生――カンブレー大聖堂の音楽組織――』 |
上尾 信也 |
85(85) |
|
|
山本 正・細川道久編著『コモンウェルスとは何か――ポスト帝国時代のソフトパワー――』 |
原田 真見 |
93(93) |
|
|
第113回史学会大会報告 | |||
|
102(102) |
|||
|
新刊紹介 | |||
|
公益財団法人陽明文庫編『法制史料集』(陽明叢書 記録文書篇 第九輯) |
前川祐一郎 |
139(139) |
|
|
藤原重雄著『史料としての猫絵』(日本史リブレット 79) |
高橋 真作 |
140(140) |
|
|
大里浩秋・孫安石編著『近現代中国人日本留学生の諸相――「管理」と「交流」を中心に』(神奈川大学人文学研究叢書 35) |
黄 東蘭 |
142(142) |
|
|
弘末雅士著『人喰いの社会史――カンニバリズムの語りと異文化共存――』 |
久礼 克季 |
143(143) |
|
|
佐藤彰一著『禁欲のヨーロッパ――修道制の起源――』(中公新書 2253) |
内川 勇太 |
144(144) |
|
|
文献目録 | |||
|
西洋史Ⅰ |
146(146) |
||
|
会告 | |||
|
173(173) |
|||